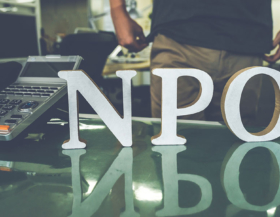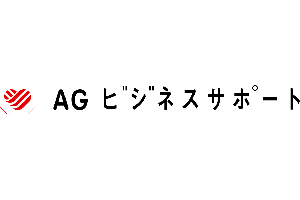法人の節税や租税回避と脱税の違いを知って税金を抑える方法5つを解説

納税義務がある法人は、節税と脱税、租税回避などの違いについて、しっかりと把握しておく必要があります。
節税と思っていた方法が「脱税」にあたり処罰の対象となってしまったり、租税回避を行ったつもりだったけれど違反行為にあたり「追徴課税」されたりする恐れがあるためです。
そこで本記事では、「法人の節税」、「法人が注意すべき脱税と租税回避」、「脱税時の罰則・附帯税」、「法人が取り組みたい節税方法」などについて、詳しく解説を進めていきます。
法人の節税とは?
法人は、1年の売り上げに対して「法人税」を納めなければなりません。しかし、法人税をそのまま収めるのではなく、「節税」することにより、支払うべき税金を抑えられる可能性があります。
まず、納付する税金を抑える方法の「節税」について、確認しましょう。
節税とは法の範囲内で税額を抑える方法
節税とは、租税法の想定内で税金の負担を減少させる行為です。節税は法の範囲内で税金を抑える方法となるため、法的に認められています。
節税は「脱税」のような違法行為ではありません。
法人の節税の例
また、法人の節税には、
- 税額控除をして税額を抑える
- 必要経費を計上して課税所得を圧縮する
などの行為があります。
法人の具体的な節税方法については、後の項目で詳しく解説します。
法人が注意すべき脱税と租税回避
続いて、処罰の対象となる「脱税」と、支払うべき税金を回避する方法である「租税回避(そぜいかいひ)」について確認しましょう。
「脱税」とは租税法に違反する行為
「脱税」とは、本来支払うべき税金を支払わない行為を指し、租税法に違反するため処罰の対象となります。脱税の違反行為として多いのが、以下の2点です。
- 売上を少なく申請する
- 架空経費を計上して出費を多く見せる
売上を少なく申請する
事業の売上があった際に、「売上を帳簿に記載せず、売上を少なく申請すること」は、脱税にあたり処罰の対象となります。
これは、「本来、法人が支払うべき税金を逃れるために、虚偽の申告をしている」ためです。
架空経費を計上して出費を多く見せる
また、「実際には支払っていないお金なのに経費として計上し、必要経費を多く見せる=利益を偽装する」ことも、脱税行為にあたります。
このような脱税行為をした法人は厳しく罰せられて社会的信用度も落ちてしまうため、事業の運営を継続させるためにも、絶対にしてはいけない行為と言えるでしょう。
租税回避は脱税と何が違う?
続いて、支払うべき税金を減らす行為である「租税回避」について解説します。
脱税は、税金の支払いを避けるために虚偽や偽装工作が行われることですが、租税回避とは合法的な行為により、税金の支払いを軽減させる方法を指します。
ただし「租税回避」は、法の抜け穴を見つけて課税対象となるのを回避する方法です。このため、租税回避は法律違反にはありませんが、「グレー」な税金軽減方法であると言えるでしょう。
また、法人の租税回避は支払うべき税金を支払わないという点で、「モラル違反である」、「処罰の対象にすべき」という声もありますが、租税法律主義(※)の観点から、現在の法律では違反行為にはあたりません。
脱税などの罰則〜附帯税の6つの種類

続いて、法人の脱税行為などが見つかった時の6つの罰則(=附帯税)について紹介します。
- 無申告加算税
- 過少申告加算税
- 重加算税
- 不納付加算税
- 延滞税
- 利子税
それぞれの附帯税を詳しく確認していきましょう。
無申告加算税
無申告加算税とは、「申告期限内に申告がなかった場合、本来支払うべき税金に対して加算される税金」です。税務署へ税金を申告せず、脱税した法人に適用される罰則です。
なお、正当な理由がある場合は、「加算税」の割合は0%となります。
無申告加算税の金額
この無申告加算税により加算される税金ですが、支払うべき税金が50万円までの部分は15%を上乗せ、50万円を超える部分は20%が上乗せされます。
過少申告加算税
過少申告加算税とは、会計上のミスなどにより、支払うべき税金を過少申告した場合に適用される罰則です。
単純な計算ミスや経費の認識の違いにより税金を過少申告してしまうと、この過少申告加算税が適用され、追徴課税されます。
過少申告加算税の金額
過少申告加算税は、「税金の差額の10%」となっています。
なお、追加で納める税金が、当初の申告納税額か50万円のいずれかの多い金額を超えている場合、超えている金額に対して15%の追徴課税となります。
重加算税
重加算税とは、本記事で紹介した「売上を少なく申請」したり、「架空経費を計上して出費を加算」したりして脱税した場合に適用されます。
隠蔽(いんぺい)や仮装の事実があり、悪意がある、脱税行為であると認められた場合の罰則です。
重加算税は35%〜40%
また、脱税行為が認められた場合の重加算税は、納めるべき税額の35%〜40%となっています。
不納付加算税
不納付加算税とは、源泉所得税を納付しなければならない期日までに納めなかった場合に適用される罰則です。
不納付加算税は10%
不納付加算税は納めるべき税額の10%となっていますが、税務署からの告知前に自己申告すれば、5%へと減額してもらえます。
延滞税
延滞税とは、税金を納付しなければならなかった期日に納付しなかった場合、日割計算で追加される税金のことです。
なお、延滞税は「国税庁のホームページ(延滞税の計算方法)」で自動計算できます。
利子税
利子税とは、事業の資金が不足している、資金繰りに困っているなどで、税金を納付できなかった場合に発生する税金の「利息」です。また、利子税を適用してもらうには、事前に税務署への申告が必要となります。
延滞税は「意図的または無意識で滞納してしまった場合に課せられる罰則」に対し、利子税とは「税務署へ税金遅延の申告をした場合に適用される追徴課税(利子)」となります。
法人が税金を抑えるための節税方法
続いて、法人が税金を抑えるための具体的な節税方法について紹介していきましょう。
- 経費の見直し
- 役員報酬を同額に設定する
- 支出タイミングの調整
- 出張旅費規定の見直し
- 中小企業倒産防止共済への加入
経費の見直し
法人の節税には、「経費」の見直しが大切です。例えば、個人のお金を会社で使う備品の購入費に利用したというような場合は、必ず「経費」として計上するようにしてください。
また、個人の車を会社で利用する場合、「商用車」とすれば、会社の経費として計上できます。仕事で利用するのであれば、ガソリン代や高速代は100%経費として計上できます。
役員報酬を毎月同額に設定する
また、役員報酬を毎月同額にしておくことで、節税が可能です。役員報酬を毎月同額にすることを「定期同額給与」と言い、定期同額給与であれば損金として計上できるためです。
支出タイミングの調整
支出のタイミングを調整することにより、大幅な節税ができる可能性もあります。
例えば、大きな黒字となりそうな年に、年度末までに設備投資などの高額な経費を使うことで、その年の利益を圧縮できるため、納付すべき税金を抑えられる可能性があるでしょう。
出張旅費規定の見直し
法人は出張費に関する規定である「出張旅費規定」を見直すことで、節税できます。出張費用は個人に対して非課税のため、所得税や住民税などはかかりません。
また、法人は出張費を「損金」として計上できるため、節税につながるのです。
出張旅費規定を整備する
また、出張費として計上するには「出張旅費規定」で、事前に出張手当などを規定しておかなくてはなりません。出張旅費規定を策定していない法人は、節税のために出張旅費規定を整備しておきましょう。
中小企業倒産防止共済への加入
中小企業倒産防止共済とは、「経営セーフティ共済」とも呼ばれていて、取引先が倒産した場合に無担保・保証人なしで掛け金の最大10倍(8,000万円)の借入ができる制度となっています。
また、この中小企業倒産防止共済の掛け金は、「損金」または「経費」として計上できるため、法人の節税に適しています。
中小企業倒産防止共済で年間240万円を損金計上できる
中小企業倒産防止共済では、毎月最大20万円(年間で240万円)までの掛金が可能で、全額が損金計上できます。
法人は節税して納付すべき税金をできるだけ抑えよう

本記事では、「法人の節税」、「法人が注意すべき脱税と租税回避」、「脱税時の罰則・附帯税」、「法人が取り組みたい節税方法」などについて、詳しく解説してきました。
節税することで事業の経営状態を安定できる可能性あり
- 法人は1年の売上に対して「法人税」を納めなければならない
- 節税をすることで収めるべき税金を減らせる可能性がある
- 節税とは法律の範囲内で認められた方法で税金を削減する方法
- 法人の節税には「税額控除」や「経費の計上による課税所得の圧縮」などがある
- 「脱税」とは本来払うべき税金を支払わない違反行為
- 脱税は「売上を少なく申告する」「架空経費の計上」などの行為がある
- 租税回避とは租税法の抜け穴を見つけて課税を避ける方法
- 租税回避は法律上合法だが「グレーな減税方法」として見られやすい
- 脱税すれば「罰則(附帯税)」により追徴課税が行われる
- 無申告加算税とは税務署に所得を申告せず、納税を逃れる違反行為
- 過少申告加算税とは、帳簿の記載ミスなどにより収めるべき税金より少なかった場合に追徴される税金
- 重加算税とは脱税が行われた時に課税される罰則で「収めるべき税金の35%〜40%」が追加課税される
- 法人は経費の見直しにより税金を圧縮できる可能性がある
- 役員報酬を同額にすることで損金計上できる
- 大きな黒字の年度に大きな設備投資を行うと「節税」効果が高い
- 出張旅費規定を整備し、出張費を「損金」として計上して節税する
- 中小企業倒産防止共済に加入することで年間最大240万円を損金計上できる
納税義務のある法人は、年間の売上(課税所得)に対して税金を支払わなければなりません。しかし、「節税」することで納付すべき税金を減少できる可能性があります。
「脱税」とは、節税とは異なり「税金の納付を逃れる」違反行為で処罰の対象となります。また、「租税回避」も税金を軽減させる方法ですが、租税回避は法律の抜け穴を見つけて税金の支払いを逃れる合法的な行為であるため、処罰の対象にはなりません。
また、脱税が見つかった場合、「無申告加算税」「過少申告加算税」「重加算税」「不納付加算税」「延滞税」「利子税」などの附帯税が追徴課税されます。また、悪意のある脱税行為として判断されれば「重加算税」が適用され、納めるべき税額の35%〜40%の金額が追徴されます。
脱税行為で追徴され、大きな損失を出してしまわないためにも、「正しく節税」することが大切です。
法人事業者の方は、ぜひ本記事を参考にしながら、「節税」「脱税」「租税回避」についての理解を深めてみましょう。